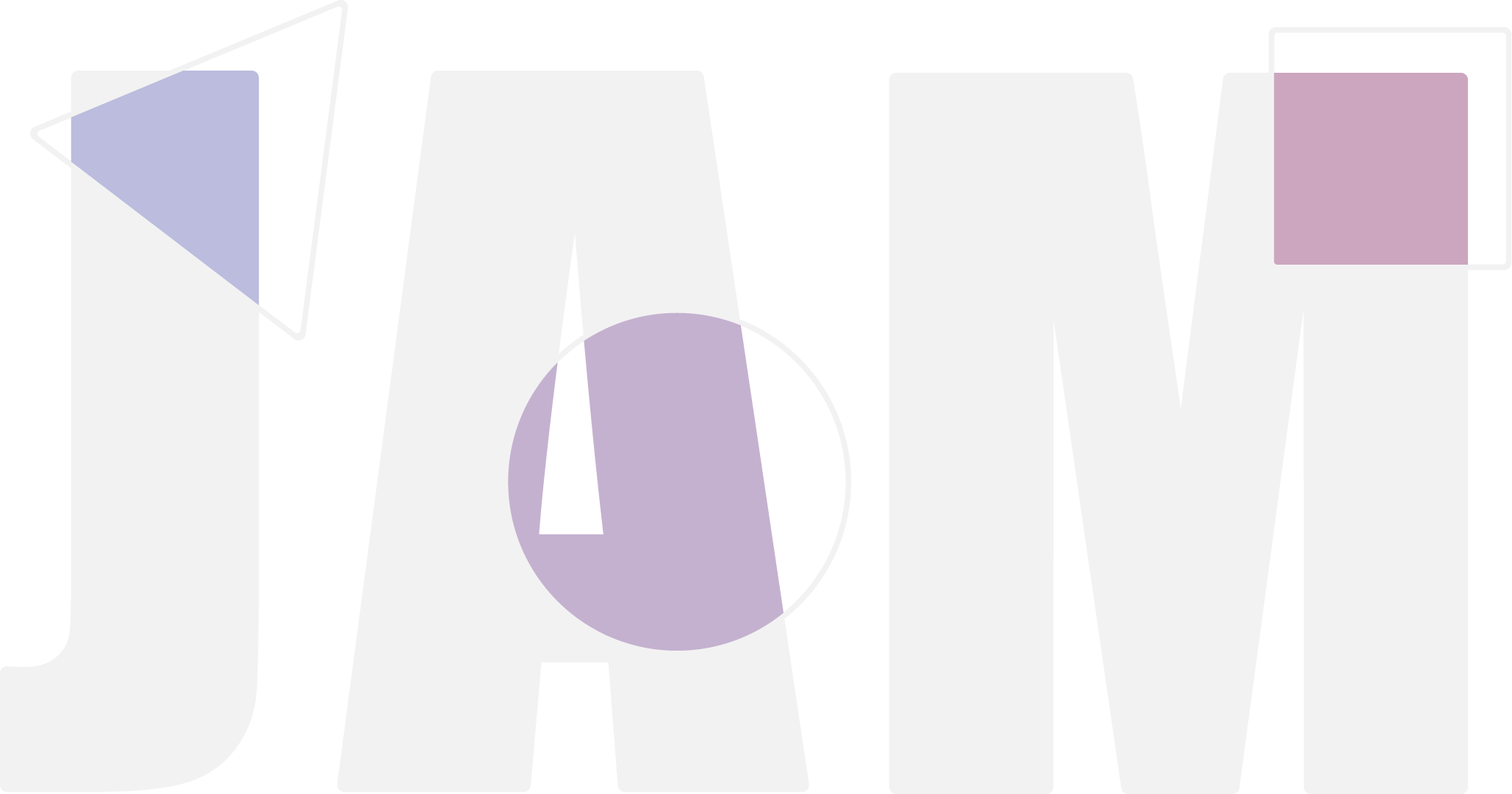JAM2025 一次審査員のたっきー 様、つじむ 様、ファレル 様、むなかた 様より、審査総評をいただきましたので公開いたします。
たっきー 様
昨年に引き続きJAM一次審査の審査員を務めましたたっきーです。今年も個性豊かで魅力的なバンドが盛りだくさんで、1ヶ月半ほどかけて全曲を丁寧に、そしてとても楽しく聴かせていただきました。
まずは二次進出が決定したバンドの皆さんおめでとうございます!かなりの数の応募がある中、この倍率をくぐり抜けて30組に選ばれただけでも相当なことだと思います。ぜひ胸を張って、でも決して慢心することなく、実地でも最高のパフォーマンスを発揮できるようさらにハーモニーを磨いていってください。
そして惜しくも一次で落選となってしまったバンドの皆さんも、決して過度に悲観しないでください。スポーツとは違い、音楽という絶対的な評価指標のない世界における勝敗など極論審査員の主観によって左右されるものです。もちろん我々審査員もなるべく公平で偏りのない審査を心がけていますが、最終的に心の琴線が動くかどうかは聴く人の感性次第であって、同じ演奏でも巡り合わせが変われば全く異なる結果になることは往々にしてあります。ですから今回の結果はあくまで一つの参考と捉えて、講評コメントの中から糧にできそうなものがあれば糧にして、ぜひこれからも自分たちの音楽を信じて歌い続けてほしいなと思っています。さて本題の総評に入りましょう。
今回は一次審査ということで、まずはアカペラの基本的な要素がしっかり押さえられているか、そしてそのうえで魅力的な演奏になっているかという視点に重きを置いて評価をつけました。ピッチやリズムのタテ、ダイナミクスの付け方といった前者の基礎的な部分に関する指摘は各バンドに個別にお送りした講評を読んでいただくとして、ここでは後者、魅力的な演奏をするための一つの大事なポイントについて綴ろうと思います。Point: 『解釈』ー1曲をいかに解像度高く理解するか
どれだけ高い演奏技術を持っていたとしても、そもそもどんな音楽を表現したいのかが演奏者になければ何も始まりません。その時に最も大事なのは『曲や楽譜をどう解釈するか』です。
たとえば一番分かりやすい例を挙げるなら歌詞解釈。このあたりは練習の中で意識している人も多いのではないかと思いますが、どんな思いやストーリーを描いた曲なのか、一つ一つの歌詞にどんなメッセージや意図が込められていてその背景は何なのか、あるいはどんな韻を踏んでいるのか…を読み解きながら歌うと、それをせずに歌っている時よりも歌が持つ説得力は大きく変わってきます。
それはリズムの感じ方やフレージングなどにも同様なことが言えます。たとえば一曲の中でのストーリー展開を意識してみるだけで演奏の起承転結の作り方が見えてきたり、一見単なるポップスのようでもブラックミュージックの影響を強く受けている曲だとしたら裏拍や後ろノリを大事にすることで心地よいグルーヴが生まれたり、楽譜上では同じロングトーンでも弦楽器をイメージしたフレーズなのか管楽器をイメージしたフレーズなのかを意識するだけでコーラスの表現の豊かさが全く変わってきたりするはずです。そしてその時に大切なのは、解釈には必ずしも一意の正解はないということです。
もちろんあまりに的外れな解釈をしてしまうと誰にも共感されずに終わってしまうので客観的に明らかな部分はきちんと押さえる(ここはまだ『解釈』というよりは『理解』の範疇ですね)ことは前提の上で、残りの余白の部分については自分たちはこの音楽をこう解釈した、だからこう表現したい、をぜひ見つけてみてください。一枚の絵画を見て感じることは人それぞれ違うように、音楽の解釈も人それぞれでいいのです。それが曲中のあらゆる箇所に表れてくるくらい歌い手の曲に対する解像度が上がれば演奏にもきっと深みが出てきますし、音楽の完成像がはっきり見えていれば必要な表現技術の習得もよりスムーズになるはずです。
ちなみにその解釈の大切さはカバー曲に限った話ではなくオリジナル曲においても共通していて、作詞作曲者自身が込めた意図を伝えることはもちろん、自分が書いた曲の音楽的なルーツは何なのか・何に影響を受けているのか…を自ら掘り下げることで、意外と今まで自分でも気づいていなかったものが見えてくることもあったりします。加えて、特にアカペラにおいて絶対に欠かしてはいけないのは 『一人一人の解釈をバンド内で持ち寄り、きちんとメンバー全員で共有し合うこと』。
たとえばリズム隊とコーラス陣でノリの感じ方が異なっていたり、繊細なバラードなのにパーカスだけが一人殴りつけるようなアタックで打ち続けていたり、リードが情熱的に歌い上げているのにコーラスの歌があまりに無表情でのっぺりとしていたり……いろいろな演奏を聴いていて時折感じるこうした『ちぐはぐな違和感』は、メンバー間での曲の解釈の不整合や解像度の不一致によって起こります。そうならないためには、お互いに曲の解釈や『こう歌いたい』を持ち寄ってコミュニケーションを図りながら、ちゃんと全員で一つの音楽を作り上げていってください。そうした意思疎通こそがアンサンブルでありハーモニーの本質のひとつなのではないかなと思っています。では、音楽の解像度を高めるために一番大事なことってなんでしょう?
それは個人的には『とにかくいい音楽をたくさん聴くこと』、そして 『その音楽の何がいいのかを掘り下げること』なのではないかな、と思っています。
ここで言う“いい音楽”とはアカペラだけに限りません。もちろんいわゆるプロアカをはじめとしたアカペラ曲もアカペラという音楽における表現の引き出しを増やすためにとても有効なのでぜひ聴いてほしいのですが、今日のコンテンポラリーアカペラがカバー文化を中心に発展してきたことを踏まえると、またそもそもの音楽の視野を広げるためにも、むしろアカペラ以外の音楽こそぜひたくさん聴いてみてください。
そしてそうした音楽を聴きながら『このヴォーカルの裏拍の子音のタメ方めちゃくちゃグルーヴィだな』とか『このスラップベースのフレージングかっこいいな』とか『この曲のラスサビの伸びやかなストリングス気持ちいいな』とか、自分なりにその良さを具体的に分析して言語化してみたり、あるいはただ真似をしてみるというプロセスもおすすめです。良さを具体的に分析するのがなかなか難しければ友達と一緒に聴いて感じたことを共有し合ってみるのもいいでしょう。素敵な音楽にたくさん触れて、自分なりに消化吸収していくプロセスを繰り返していくうちに、それがきっと血となり肉となり自分の音楽となっていくはずです。
最後になりましたが、同じアカペラという音楽を愛する仲間として、ぜひこれからもこの音楽を楽しみながら新たな可能性をともに追求していきましょう!
つじむ 様
今回JAM2025一次審査で審査員を務めました、つじむと申します。総評ということで、私からは2点書かせていただければと思います。
①自己紹介としての選曲を
最近でこそオリジナル曲を歌うグループが増えてきましたが、今回JAMに応募された皆さんに限らず多くの方は既存曲のアカペラカバーを主軸に練習・活動をされていると思います。そして、時代を経るごとに皆さんを悩ませるのがおそらく選曲ではないでしょうか。世の中には新しい音楽が出続け、かつ一度出た音楽は基本消えることはないため、良くも悪くも選択肢は増えていきますね。カバーにおいてよく起こるのが、「この歌はもうこのグループが歌っていたから」、「あのバンドのようには歌えないから」、「他と被るかもしれないから」というような思考です。もちろん理由は色々あると思いますが、昨今”どこから見つけてきたんだろうか”というような物凄くニッチな選曲をするグループが増えてきたように思います。
それを否定するわけではないですし、個人的には新たな音楽の発掘にもなって有難いのですが、少し考えてみていただきたいのが、”自分たちという存在がそもそも被らないのに、それを強みにしようとは考えないのだろうか?”というところです。コンペティションにおいて、たしかに他の挑戦者との差別化を検討することは重要です。JAMでいえば数百バンドの中から約30バンドしか次に進めないわけで、上手なだけで勝ち上がれるほど単純な闘いではありませんから。しかし、その差別化を選曲の方向性だけで済ませて終わりというのはやや安直ではないでしょうか。「この楽曲を歌うグループ」というだけの売り出し方は、自己紹介のようでいてその楽曲の他己紹介どまりだと思うんです。皆さん自身がアカペラカバーすることが演奏・パフォーマンスにおける最大加点になれば良いなと感じました。
②スキャットの取り扱いについて
楽譜にある情報を出力するというのは演奏における基本ですが、皆さんは楽譜を読む際、何のためにooにしているか・ahにしているか等について考えたことはありますか。楽譜に書いてあることを自分の声で再生する音読としての”読む”以上に、内容理解としての”読む”が皆さんにはもっと必要なのではないかと感じました。ドラマの台本に例えると分かりやすいかもしれません。台本に泣く演技について指示があったとして、たとえばそれがアカペラの楽譜においての「ah」だったとしましょう。これを俳優さんや声優さんがただ何も考えずに音としてのみ再生するかいう話です。おそらく前後の脈絡やストーリー、周りのキャラクターとの関係性などを考えた上でニュアンスを落とし込むものと思います。アカペラにおいてはリードボーカルが比較的それをしやすい立場といえます。ではコーラスはどうでしょう、ahは歌詞ではないからと急にその解像度が落ちてしまっていませんか?
今回応募いただいた皆さんの中には、端的に言うならば台本に泣けと書いてあったから泣いた=楽譜にahと書いてあるからahと歌った、としか説明がつかないような、裏付けの心もとない演奏が散見されました。これは自戒でもありますが、アカペラって何も意識せずに演奏すると高確率で”ダサさ”に着地すると思うんです。私も時々「dalatta-ha〜って本気の顔で歌ってるのダサくない?」と我に返るあります笑
今の話は半ば冗談ですが、スキャットというのはそれだけ個性的な音色であって、扱い方次第ではダサくもなるし唯一無二の輝きにもなるということです。それを知っているかどうかで、取り組み方はだいぶ違ってくると思います。練習の際には、是非楽譜に書いてある文字としてのスキャット情報にとどまらず、そこに書いていない情報をいかに音・表現として出力できるかということに注力し、より演奏に説得力を持たせることを目指してみてください。何だか後半演技論のようになってしまいましたが……ある種皆さんも演者ではあるわけなので、楽譜をよく読み込み、いかに表現にとして舞台上に持っていくか主体的に是非考えてみましょう。皆さんの今後の活動に還元できそうなことがひとつでもあったら幸いです。改めて今回はJAM2025一次審査に携わらせていただきありがとうございました!
ファレル 様
ご応募いただいた皆様、ありがとうございました。一つ一つの音源に対して様々な感想を持ちましたが、全体講評としてある程度まとめたものを記載します。書ききれないものがあるうえ、長文になりますがご容赦ください。
今回評価が分かれた点をあえて抽象的に示すと「演奏に説得力があるか」です。
表現、歌唱技術、メンバー構成、曲、アレンジ、録音環境など、演奏を構成する要素は多岐にわたります。それらの要素において、何をどういった理由で選択したかが重要です。何となく選んでいたり、細部までこだわっていなかったりすると演奏の節々に粗さとして表出します。またちゃんと選択をしていても、それが音楽的に正しくなかったり、個々の強みにかみ合っていなかったりすると、粗さとまでは言わずともどこか刺さらない、良くも悪くも「上手い」演奏になります。自分たちの選択にいかに説得力を持たせられるかというのを、改めてバンドメンバーで目線合わせしてみてほしいです。ここからはその選択において必要になるであろう要素を全体+各パートに分けて記載します。
■全体
・表現の幅
本来0~100%の表現の幅がある中で、50~80%程度に収まる演奏が多かったように思います。フルで幅を使い切れということではありませんが、1番でMaxが来てしまい2番もラストも同じテンションだと聴き手の期待を超えず、慣れによってむしろ右肩下がりになってしまうこともあります。どのように盛り上げていくのかをグラフで可視化して共有すること、極端に抑揚をつけてそこから落とすことを練習に取り入れてみると、全員の意識が統一されて、演奏に表現が乗ってくると思います。また聴覚情報のみの音源審査においては少し表現を大きめにする意識があってよいかもしれません。・縦と横
縦をそろえることと横の流れを作ること、それぞれに意識を割きたいです。縦は拍のどこに何の音がどのようなスピードで入るのかをそろえること、横はそれぞれが歌うラインをフレーズとして捉え、波のようにあえて流していくことです(個人的な定義です)。縦がそろっていないとずれているなと感じますが、強すぎるとすべてがはっきりしてしまい、機械的な表現になります。そこに横の意識を持てると表現を乗せつつ、リズムも作れている状態になります。
楽譜に対して正確に演奏しようとするとよく縦だけになることがあります。ただ楽譜を正しく演奏するのであれば楽譜再生アプリでよいです。楽譜をどう表現に落とし込むのかが人間の行うアカペラの意味ではないかと思います。・録音環境
各パートがバランスよく聞こえるということは非常に大事です。ミックスが必須だとは思わないのですが、生声でベースが聞こえない、反響が極端に強くて特定のパートだけ聞こえるなど、審査がしづらい音源が見受けられました。歌唱の実力以外の部分でマイナスになることは非常にもったいないので、録音環境には気を配ってください。また演奏の前後の会話や「いきまーす」といった合図のカットもお願いします。審査の場においては明確にノイズです。■リード
・キー設定
無理に原曲キーで歌う必要はありません。キーが合っておらず、後半で体力が持たない、最高音あるいは最低音が出ないケースが見受けられます。自分の歌唱の魅力が最も発揮されるキー設定をしましょう。・原曲との差分
ほとんどがアーティスト楽曲のコピーですが、コピー元のアーティストのイメージが強ければ強いほど、自身の個性を出さないと、比較されて負けてしまいます。練習するには完全コピーするのが効果的ですが、本番で歌うのは皆さんです。自分が歌うからこそ原曲と違った良さが出るという状態を目指してください。・力配分
序盤から飛ばし気味な方が多かった印象です。やはり曲の展開としてはラストに向けて盛り上がっていってほしいのですが、「表現の幅」でも書いたような1番からほぼMaxの状態になり、ラストで上げるほどの力が残っていないことがよくあります。リードは表現を一番重く担うパートなので、その前提で曲をどのように歌い切るのか考えてみてください。■コーラス
・歌唱する意識
コーラスは伴奏ではありますが、表現をしなくてよいわけではありません。むしろ伴奏こそ歌唱する意識を持ち、しっかりと表現をつけるべきだと思っています。リードの表現を補助したり、リードのない部分ではメロディーとして目立つ必要があります。リードができないからコーラスをするのではなく、リードもできるけどコーラスをしている状態が理想ではないかと思います。・母音の種類
母音の種類が少ないあるいは日本語母音に偏っている方が多く、その影響で表現の種類も減ってしまい、平たい歌唱になるケースが見受けられました。曖昧母音をうまく活用し、多様な発音を持って表現をつけてほしいです。また子音の発音も同様です。■ベース
・音の正確性
ベースは音を外したら終わりぐらいの気持ちでいましょう。ピッチがぶれることはあるにしても、音程を間違えているというのは厳しい言葉を使うと論外です。和音のルート音を担うことの多いベースが何度も外すと、いくら他のパートがうまくても曲として成立しないので、評価がガクッと下がります。誰よりも音にシビアでいましょう。・フレーズ感
前述した横の流れを意識し、フレーズとして音を捉えられるかどうかで、ベースのメロディー感が大きく変わります。一音一音すべて同じ発音とアタックで、平坦かつ機械的な演奏になるケースが一定数見受けられました。ベースはただ音が当たっていればよいのではなく、表現力も必須です。リードのような歌詞もコーラスのようなスキャットもなく、表現をつけるのが難しいですが、だからこそベースは歌心が一番必要なパートだと思います。そのためにも音をフレーズで捉えることを意識してください。・音色選び
どのような楽器あるいは声で歌うかを場面ごとに定めていますか?ギターベース、コントラバス、4thコーラス、ティンパニなどなど、声であるがゆえに様々な音色を選ぶことができます。ただその音色変更が意図せず起こっている、あるいは音色が楽曲に合っていないケースが多く見られます。どの音域でも意図した音色で鳴らせるような歌い方を模索してほしいです。またバラードにおけるリムショットもリズムの指標としてただ鳴らすのではなく、音色にこだわってください。■パーカス
・音色選び
曲に合った音色は何かを徹底的に研究してください。バス、スネア、ハイハット、クラッシュなどそれぞれの高さ、重さ、長さ、音量バランスといった音を構成する要素をこだわりきれるかで曲に与える印象が大きく変わります。特にクラッシュの高音が強すぎて同じドラムセットにはない音になっているケースが多かったので注意してほしいです。・カウント
カウントから曲のリズムと雰囲気をすべて作りきってください。バラードで歯切れよくカウントしたり、アップテンポで落ち着いたテンションでカウントしたりすると、聴き手の想定と違う歌が始まってしまいます。そして歌い手にとってもそれは同じです。カウントでこの曲を始めるのだという提示をし、全員がイメージを共有できる状態を目指してください。以上です。この講評が皆さんの演奏力向上のヒントやきっかけになればと思いますが、あくまで講評でしかありません。試行錯誤を重ねることの方が遥かに重要です。講評をうまく活用しつつ、様々なアプローチで音楽を探求してみてください!
むなかた 様
総評をご覧いただきありがとうございます。
この文章に目を通してくださっているあなたは、きっとアカペラに没頭し、日々情熱を注がれていることと思います。そんな方々にとって、声だけで音楽を奏でることは、もはや当たり前の感覚になっているかもしれません。だからこそ、この機会に少し視点を引いて、アカペラという表現方法の意義を改めて考えていただければと思います。まず大前提として、アカペラは極めて制約が多く、かつ不安定な演奏スタイルです。現代には魅力的な楽器が無数に存在する中で、皆さんはあえて「声だけ」という手段を選択し、構成上の制限を受け入れています。ましてや、ドラムの音まで口で演奏するという発想は、常軌を逸していると受け取られることすらあるかもしれません。加えて、アカペラは安定性においても楽器演奏に比べて不利な側面があります。一例として、多くの楽器は音程と音量をある程度独立して制御できるのに対し、声は両者が緊密に関連しているため、わずかな息づかいの変化でも音程が揺らぎやすく、アンサンブル精度の障壁となることも少なくありません。このような厳しい制約を背負ったうえで、演奏スタイルとしての説得力を持たせるには、「声だからこそ可能な表現」を最大限に活かす意識が不可欠です。この前提を踏まえ、今回の音源審査を通じて特に印象に残った3つの観点について述べさせていただきます。
まず「スキャット」について。スキャットはアカペラの醍醐味とも言える重要な表現手法です。ただし、楽譜上のスキャットを機械的になぞるだけでは、その効果は十分に発揮されません。たとえば「ah」という一音にしても、明るく開放的な響きと、柔らかく広がりを持つ響きでは、まったく異なるニュアンスが生まれます。スキャットに込められた意図を考え、それを自分たちの表現としてどう昇華させるかをもう一歩踏み込んで追求していただきたいと思います。
次に「抑揚」について。本審査では、抑揚を声量の大小のみで表現しようとするグループが多く見受けられました。もちろん声量は重要な要素ですが、それだけでは表現の幅が限定されてしまいます。息のスピードや混ぜ方、響かせる位置、喉の開き方、さらにはアタック・リリースといった要素も含め、声には多様な表情があります。これらを有効に活用できれば、演奏をより立体的なものにできるはずです。
最後に「編曲」について。本審査では、ユニークで創造性に富んだ編曲が多く見られ、それ自体は非常に素晴らしい成果だと感じました。一方で、演奏一発で聴き手に伝わるかという観点では、再検討の余地があるグループも散見されました。「音楽に正解はない」という台詞を耳にすることがありますが、聴き手が編曲の意図を無条件に汲み取ってくれるとは限りません。編曲は自由であるべきですが、その自由には”聴き手への配慮”という責任が伴うことも忘れないでいただきたいと思います。
皆様には、今後も人の声がもつ独自の表現力を大切にし、その可能性を丁寧に掘り下げていっていただきたいと思います。本審査が、通過・落選を問わず、エントリーいただいたすべての方にとって意味のある経験となり、次なる挑戦への糧となることを心より願っています。
※審査総評は審査員の皆様の50音順で掲載しております。
改めまして、審査員をお引き受けくださいました、たっきー 様、つじむ 様、ファレル 様、むなかた 様に深く御礼申し上げます。
ご質問やお問い合わせは CONTACT よりお願いいたします。
引き続き Japan A cappella Movement をよろしくお願いいたします。
Japan A cappella Movement 2025 実行委員会