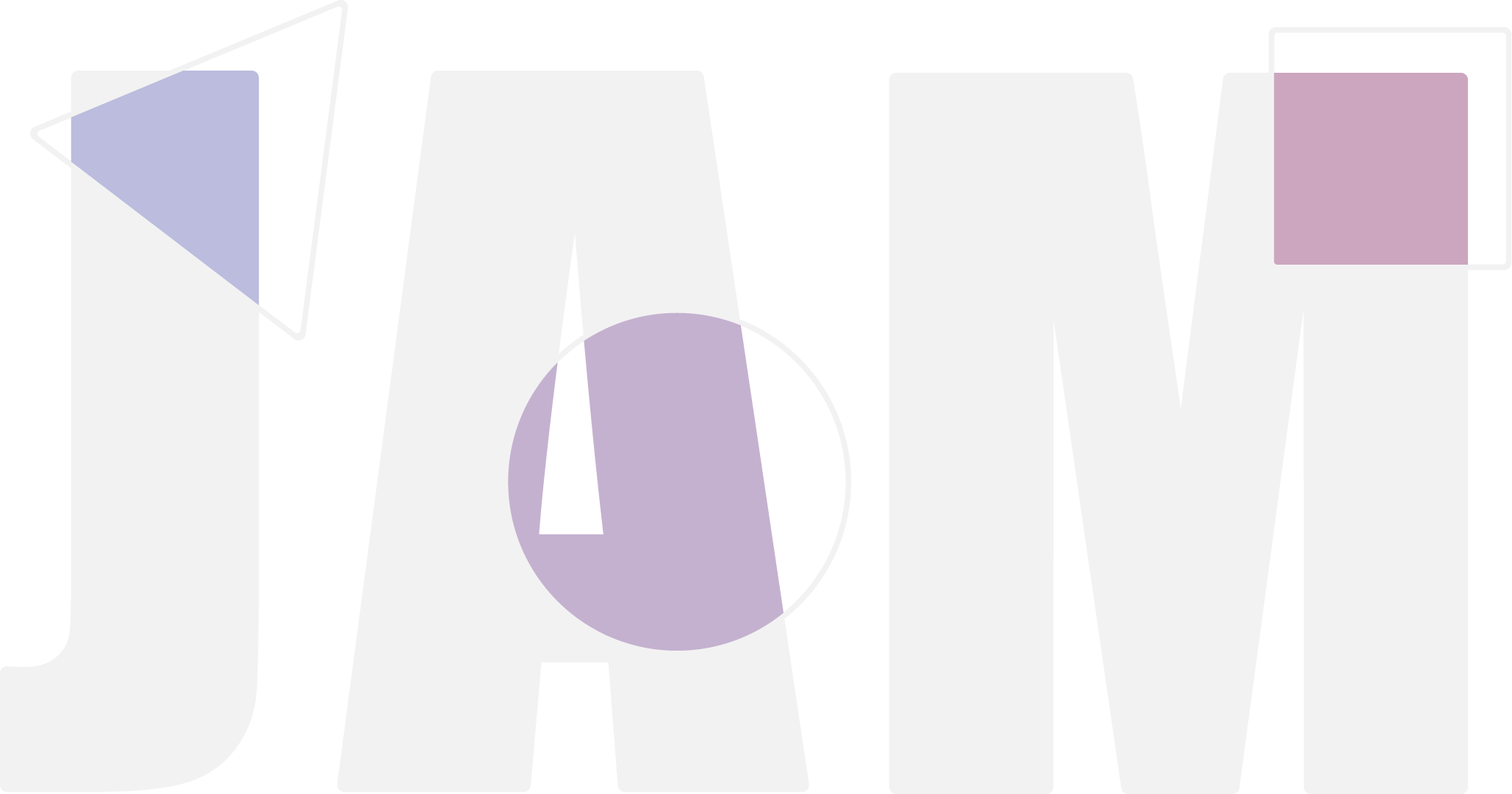JAM2025 二次審査員の、shio 様、加藤ぬ。様、引地洋輔 様より審査総評をいただきましたので、公開いたします。
shio 様
皆様、二次審査大変お疲れ様でした。
最初に何バンドか聴いた時点で思ったよりクオリティが高く、後から審査基準を引き上げることになるほど、どのバンドもいい演奏をしてくれたライブだったと感じています。総評ということですが、いいことばかり書いても仕方がないので、感じたことのうち改善可能な点をたくさん書こうと思います。
自分自身現役時代に講評でボロボロに書かれてめちゃくちゃ腹が立った経験があるのですが、逆に「めっちゃいい感じです!」だけ書かれても成長はなかったので今では感謝しています。総評でも個別講評でも、「全体的に良かったかどうか」と「書かれている改善点の数」は特に関係ありませんのであまり気にしないでください。全体
今回の私の審査基準は端的に言うと以下2点です。
基準① バンドが何がやりたいのかを、聴き手が理解できる
基準② 上記やりたいことがわかった後、聴き手が期待したものに対して正しく応えている演奏が上手いことやアレンジが良いことはあくまで手段であり、大前提の基準を満たすためであれば他の手段でも構わないと思っています。
これが審査でなければ、「難しいことにチャレンジするために集まって、ちゃんとはできていないけどやっているだけで楽しい」というので全く問題ないのですが、今回は審査であり、尚且つ通過したら本戦という一般の方にも見ていただくステージに出るわけなので、上記2点にこだわっています。
一つ例を挙げれば、「なんかめちゃくちゃ上手そうな雰囲気があるけどよく見るとコンセプトはふんわりしており、演奏も他のバンドと比べたらそこそこ上手いが最初の『上手そう』の予想は超えてこない」ようなバンドは明確に減点しています。上手そうなバンドならめちゃくちゃ上手くあって欲しい。(ちなみに演奏技術やアレンジについてはかなりレベルが高く、だからこういう部分の話ができているという側面もあります。ピッチがめちゃくちゃとかコードが間違っているなど「そもそも論」はもちろんあるので、それを乗り越えた上でという話なのですが、少なくとも通過バンドのラインを引くにあたり関係がありそうなバンドにおいてはそのレベルの話は考える必要がありませんでした)
具体的にいくつか例を書きます。
世界観
衣装や登場時の雰囲気、1曲目の入りの音をちゃんと鳴らすことなどによって、バンドの世界観や技術力をしっかり伝えてもらえると聴く側は安心して聴けるようになります(基準①)。逆にそうでない場合、聴き手は「これは何を聴いているんだ?」というのを考える時間が生まれてしまいます。
その上で、基準②について、明るいコンセプトなのに表情が硬いとノリきれなかったり、シビアなコンセプトなのにMC中動いたりすると集中力が切れたりしてしまいます。リードがフロントマンとして主導するバンドなら、リードが目立つ衣装やステージングを期待します。大きな単位でのダイナミクス
演奏は非常に上手いが同じテンションがずっと続くので16小節ぐらいで飽きてしまったり、落とすべきところでしっかり落とせていないが故にサビで盛り上がりきれなかったりするバンドが目立ちました。1曲を通して(場合によっては曲を跨いでステージ全体を通して)全体のストーリーを引いて、それに応じたダイナミクスを作り、バンド全体で表現すべきです。
これは、聴き手に対して視線や感情の動線を用意しておいてあげる(ここでコーラスを聴かせる/ここで圧倒する/ここで泣く)話とセットだとも思います。
バラードのバンドだと音圧的に不利になると思いがちですが、聴かせどころをしっかり聴かせることによって強烈なインパクトを与えられるはずです。お客さんに届く音を意識
日頃の練習から全てスタジオでできる訳ではないと思いますが、実際に聴き手に届く音が最終的な作品となるので、そこをゴールに持っていってほしいと思います。機材練でマイキング含め録音して聴き直すとか、自分たちの特性を理解してPAシートを適切に書くなどはまず行ってほしいです。それから、二次オーディションはライブハウス、本戦はオープンなステージという違いもあります。本戦ではリハーサルの時間もちゃんとあります。アレンジして上手に歌うことがゴールではなく、お客さんの耳に届け切るところまで意識して作っていってもらえればと思います。
総じて、アカペラをやっている当事者が色々考えている細かい点はあくまで細かい点であって、聴き手に対してはもっとマクロな所の方が優先順位が高いです。自分たちだけでは視野が狭くなるとも思うので、適宜バンクリなどを活用しつつ客観視できると良いと思います。
個別のパートの話
以下は上記の話と比べて各論ではあるのですが、比較的多くのバンドに共通して思ったことなので雑多に書きます。
リード
全体的にコーラスに埋もれてしまうリードが目立ちました。思っている以上に歌詞をはっきり噛んで発音することと、低音でのマイキングを工夫することはまず意識できるかなと思います。曲中MCが聞き取れないなどもアカペラあるあるですね。音量/マイキング/PA等でコーラスをがっつり下げる等も選択肢にあります。
コーラス
まず、和音感を出す上で「一音一音、入りは弱くて後からクレッシェンドする」という歌い方はかなり良くないです。鳴り始めるまでに時間がかかりますし、横のフレーズ感も無くなってしまいます。「一音目は頭からしっかり当てる」「二音目以降はレガートに歌えるようにする」等で練習できるといいと思います。
加えて、みなさん発声を工夫しているからか倍音がしっかり出ているのですが、倍音が出過ぎてコード感がわからなくなっている場面も散見されました。マイキングが遠いと近接効果で高音成分が増えてしまうので注意しましょう。
また、中低音域が空いてしまうことによって空間を埋めきれていないバンドもありました。アレンジにおいてコーラスの一番下のパートの音域を気を付けることや、発声/マイキングの工夫によって、ベースとの間を埋めることを意識すると良いと思います。ベース
先に結論から言ってしまうと、ベースは原則的に音が下がるに従って音圧を上げてほしいなと思っています(理由後述)。音域の問題で無理をして最低音付近で音量が下がってしまうと、楽曲全体のバランスが崩れてしまいます。普通にしていると高音の方が発声しやすく音量バランスが逆転してしまうので、かなり意識する必要があると思います。また、ベースでフォルテを出そうとした時、声帯を閉鎖すると、倍音が増え低音成分が減ってしまいがちなので、息の量をしっかり確保する必要があると思います。(音域が下がるにつれて音量を出したい理由)
・外声反行の原則的に、リードや高音が上がっていく(≒盛り上がっていく)時に低音は下がるのが自然
・(密集配分に対して)開離配分はダイナミックな展開な部分で使われがちパーカス
今回の審査を通して、全体のアンサンブルの中で圧倒的に気になったのはタイム感でした。もちろん音色やテクニック等もあるのですが、音楽として考えたときに、タイム感がしっかりしているバンドが圧倒的に気持ちよかったです。自分はベースがメインですが、主役がリズム隊ではないところでリズム隊が気になったらその時点で負けだと思っているので、ヨレ等を感じさせずに安心してリード等の主役を聴かせてくれるのが必要条件だと思っています。
最後になりましたが、全バンドがこの日のために万全の準備をしてきたことがすごく伝わってきて、感慨深かったです。こちらも真剣に向き合わせていただきました。
通過バンドもそうでないバンドも、いい音楽を追求して、アカペラ界を盛り上げていってもらえたら嬉しいです。
加藤ぬ。様
総じて練度が高く、音楽への実直さを感じさせる演奏が多かったです。
特に
「和音を鳴らして演奏する」
といった、アカペラ演奏におけるとても大きなハードルを超えているグループが多く、これは本当にすごいことです。とても真面目に楽譜と向き合って、丁寧に練習している姿が自然と目に浮かびました。今後もぜひ、その姿勢を大事にしたまま、音楽を突き詰めていってほしいと思います。
ただし、演奏のレベルが高い一方で
「上手だけども、何かが足りない演奏」
の存在が気になりました。楽譜通りに、正しい音を、正しいリズムで歌っているのに。
これは何かがおかしい。感情が動かされないのです。
サプライズがないのです。
ステージ上で閉じた表現になっているのです。これは一体なんなのだろう?と考え続けた結果、
「プレゼンテーションが不足している」
という言葉に、たどり着きました。
・この場をどういう空間にしたいのか?
・このステージで、何を感じさせたいのか?
・この曲で、何を感じさせたいのか?
・このセクションで、何を感じさせたいのか?
・このフレーズで、何を感じさせたいのか?
・この言葉で、何を感じさせたいのか?
・この音で、何を感じさせたいのか?
そして、
・”自分は”何を感じているのか?
・”自分達は”何を感じているのか?それが伝わってこないのです。
見えてこないのです。もし
「楽譜通り演奏できるか選手権」
であれば、提示がなくても構わないと思います。でも違いますよね。
表現である以上、その場は何かしらの表明、プレゼンテーションであるべきです。
(↑これは、私の”プレゼンテーション”です)「メッセージ性が~」とか、高尚なことを言いたい訳ではありません。
もっと、根本的なところです。
「意思を示して欲しい」のです。ステージで演奏するというのは、聴き手の注意を引き付け、時間を奪う行為です。
その引き換えに、あなたたちは何を提示するのか?主張が不足していると、聴き手は受け止め方が分からない。
「これ何の時間?」となってしまいます。——————————————————————————————
全体的に演奏レベルが高かったからこそ、総評は「プレゼンテーション」に焦点を当てて書かせていただきました。
もちろん中には、ここまでの内容とは逆に
・プレゼンテーションは濃密だが、技術が足りていないグループ
も、あります。正直に言って、審査員としてはこれが一番心苦しいポイントです。
もし技術が伴っていたのであれば、本当は、プレゼンテーションが濃密なグループを本選に送り出したい。だから、そういったグループには、もっともっと上手くなっていただきたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
引地洋輔 様
出演者の皆さん、スタッフの皆さんありがとうございました。
みんなすごかった。驚いたのは現地でのマイクリハーサルはなし、ということ。
それであの演奏が並ぶってどういうことですか??
回を重ねるごとにレベルは上がり、どんどん演奏が洗練されていくので、マイクの使い方で差がつく、つけるしかない部分もありました。
生声でしか練習していなかった自分の時代からすると、驚きだらけです。一方で、考えたこと。
実は昔の方が審査は難しかったのではないか。
「こことここを同じ土俵で比べるって無理でしょう!」
みたいなことが、今はなくなってきている気がします。
アカペラ知識、練習方法から楽譜に至るまでいいものがすぐに共有される今と違って、すべては手探り!お手本も他のエリアとの交流もなし!という時代は、サウンドもステージングも凸凹なバンドが並んでいましたから。
「昔の方が良かった」と言う人がいるなら、その凸凹な楽しさのことを指しているのかな、と思いました。(あとは強めの思い出補正。確実に今の方が平均レベルは高いので)
前置きが長くなりました。以下、考えたことを少しだけ例を挙げて書きます。
気にしても気にしなくてもいいです。好きなことを好きなようにやって欲しいというのが一番の思いです。
個別にバンド講評もお送りしましたが、それよりも自分たちの「好き」が優先されるべきです。
毎度のことながら演奏の技術論には触れません。演奏技術はどうでもいいというか、当たり前でしょうから。
一次審査の総評でもいいことたくさん書いてありましたよね。
録音物の一次審査と違って、二次はお客さんのいる環境での生演奏審査でした。
本選が池袋駅前のオープンスペースということも意識して、生アカペラを聴く側を軸にして書きますが、これはアカペラ演奏者が「わかっていないこと」ではなく、「忘れてしまっていること」かもしれません。ちなみにJAM第一回に出た当時の自分はまったく考えていないことです。(笑)
皆さんはアカペラの生演奏でメリハリをつけたい時に何を取り入れようと考えますか?
リードチェンジ、ダイナミクス、テンポチェンジ、動きでの変化。
全部正解ですが、聴く側にとってのメリハリは他にもあるのです。
ベルトーンやアルペジオと呼ばれる技法がありますね。
アカペラだと一人ずつ声を順番に重ねていってハーモニーを作るコーラスパターン。
とてもオーソドックス、シンプルな技法です。
あれを取り入れる効果ってなんだろうと、考えたことありますか?
コーラスのパターンに変化をつけるため??それよりも「誰が何をやっているかがすぐわかる!」
聴く側にとって素晴らしいのはそこです。目の前の生演奏なら特に。
ピアニストの左手がアルペジオ演奏するのと、アカペラで一人一音鳴らしてリレーするアルペジオは伝わる情報がまるで違うわけです。
皆さんが初めてアカペラ演奏を生で聴いた時に誰がどのパート、どの声か1曲で認識できましたか?ハーモニーが塊で気持ちよい演奏ほど、誰がどのパートかわからなかったのではないでしょうか。
普通の楽器バンドなら、誰が何をやっているかは楽器を見ればわかります。一方パッとわからないのがアカペラ。これは乱暴に言うとストレスです。
それを利用していくだけでもメリハリはつきます。
・歌い出しのサビが全員字ハモで決まっていて気持ちいい!でも誰が何やってるの?
・と思ってたら、その後の平歌部分で一人ずつ重なっていったからわかった!
その後にまたサビが来た時、歌い出しと全く同じものを聴いても印象が違うわけです。さっきより個人を認識した上でハーモニーを楽しめる。
これもメリハリです。
楽譜通りに正しく歌っているのに、なにか足りないと言われることがあるなら、発声とか音色とか以前に「生で届く情報は何か?」を考えることにヒントがあるかもしれません。
話を二次審査会場に移します。聴く側としての印象のこと。今回めちゃくちゃいい声、ベースマンらしい低音ボイスを聴くことができました。
すごかった。おじさんなので、ロッカペラのバリーさん思い出しました。
その低音の魅力に気づいたら、もっと欲しい!と思うわけです、こっちは。
別に何小節もソロをやるのでなく、むしろ一発サビ前の1拍だけでもズドーンと。
それだけで客席は沸きます。ハイトーンボイスでもまたしかり。
もちろん、やらなかったからと言って減点にはなりません。
品のあるスタンスだと理解します。でも加点ポイントになるところだよなぁ、と。
一人一音しか鳴らせない制約があるアカペラは、一音で見せ場を作ることもできます。
そういう面で、外部による秀逸なアレンジを演奏するときであっても、そこに「このメンバーならひとつこれ足してみようか」という追求はしていただきたい。あるでしょ?足したくなるところが。隣で歌うメンバーに。
閑話休題ロッカペラという単語書いたので、「ロッカペラ サンディエゴ 1993」で検索してみてください。
テレビの歌唱なのでカメラワークありますが、目の前にいることを想像しながら観れば、伝えたい要素が伝わる気がします。一発鳴らすベースの効果、声色を整える、とは別のサウンド作り。
えぇ、僕がこれまで書いたことが無駄だったんじゃないか、と思うくらいに。さて、今回聴かせてもらった中には、しっかりとした演奏技術に加えてこういう要素を上手に取り入れているバンドがあって痺れました。
リードが自然に近づいてきて、その声に虜になったらサッと引いてコーラスが主役になりそっちを見てたら、端から指で打つスナップをマイクに入れる技が始まったり、ベースがしれっと隙間でハイハット刻んだり。それを気づかせるさじ加減も絶妙。
忙しい!楽しい!なんて上手にもてあそんでくれるんだろう、と。
あくまでも自然な音楽の流れで、それやられたらまだまだ聴きたい!
と思っていたらお時間ですって?あぁすてきな恋泥棒。
音源ではここまでの気分になれないだろう、と感じるお手本のような生演奏。
素晴らしかったです。
まだまだ感心ポイントあるんですが、こちらもお時間ですかね。
最後に。
ここまで書いてきたことを27年前の自分が読んだらどう思うだろう、と想像しました。おそらく「はいはい、わかりました。でも好きにやるわ。なんなら真逆の発想で個性をいっさい聴かせない、まるで一人アカペラ!と思うような、おそ松くんバンド組むわ」とか言いそう。若き日の自分、それでいいよ。
皆さんもどんどん好きなことやってみてください。
効率よく正しく楽しい練習の先にある、あなたの世界を本番でぜひ。
気が向いたらRAG FAIRツアーにも遊びに来てください。
JAM2025本選の大成功を願っています。
※審査総評は審査員の皆様のアルファベット順ならびに50音順で掲載しております。
改めまして、審査員をお引き受けくださいました、shio 様、加藤ぬ。様、引地洋輔 様に深く御礼申し上げます。
ご質問やお問い合わせは CONTACT よりお願いいたします。
引き続き Japan A cappella Movement をよろしくお願いいたします。
Japan A cappella Movement 2025 実行委員会